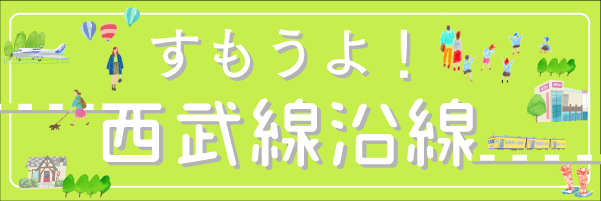【イベント報告】所沢の名店とのコラボで実現!「Hanako w/ Seibu-おいしいワークショップ-」レポート

Hanako w/ Seibu https://seibu.hanako.tokyo/
「私が出会ったお店と、その暮らし。」と題し、西武線沿線の美味しいお店や素敵なコミュニティを、店主=「ひと」にフィーチャーする形で紹介していきます。
自家焙煎珈琲店〈Kieido〉の店主・寺内さん直伝! おいしいコーヒーの淹れ方。
今回のイベントで、コーヒーの淹れ方を教えてくれたのは、所沢にある自家焙煎珈琲店〈Kieido〉の店主・寺内英貴さん。寺内さんはご自身のお店のことを「研究者がやってるコーヒー屋」と初めに紹介しました。というのも、寺内さんは農学博士の研究者というとってもユニークな経歴の持ち主。小学生の頃からコーヒーに興味を持ち、淹れ方やハンドピック(豆を選別)など、どんどんコーヒーにのめり込んでいき、とうとう会社を辞めて、お店を開くという夢を叶えました。

そんな寺内さんの淹れるコーヒーは「透明感があって、まろやかで、やさしい」コーヒー。すっとのどを通って、香ばしい香りが鼻腔に残り、「コーヒーってこんなにおいしいんだ!」と感動するおいしさです。そんな寺内さんのおいしいコーヒーを淹れるテクニックを余すことなく、教えていただく1時間が始まりました!

まずは、事前に参加者に送られたという道具の紹介から。ミル、ドリッパー、サーバー、ペーパーフィルター、コーヒー豆は寺内さんの焙煎によるブレンド豆を2種(ホット用とアイス用)。これらに加えて、キッチンスケール、お湯をわかすやかん、温度計を各自ご用意いただきました。また、事前準備としてお湯を2リットル沸かしていただき、アイスコーヒー用の氷も用意していただきました。

今回は、ホットコーヒーの作り方に加えて、アイスコーヒーとカフェ・オ・レの作り方や、コーヒーがぐっとおいしくなる魔法のお湯の作り方をレクチャーしていただきます。参加者も一緒に寺内さんのやり方を真似ながら、コーヒーづくりを楽しんでいきます!
“魔法のお湯”とは? おいしいコーヒーにするための豆知識が盛りだくさん!

まずはホットコーヒーの淹れ方からレクチャーいただきます。今回ご用意いただいた「Kieidoブレンド」はブラジル、グァテマラ、コロンビアのブレンド。「飲み始めは深煎りのコロンビアのやさしい苦味が感じられ、途中から消えてグァテマラにスーッと流れていく」という寺内さん自慢のブレンドです。
〈Kieido〉さんのコーヒーに感じる透明感の理由は、雑味や渋味を排除することにありました。
「初めにサーバーに注いだお湯は濃い状態ですが、だんだんと薄まってくると雑味、渋味、余計な苦味が出てくるんです。なので、まず初めに淹れたおいしい部分だけを使って、お湯で希釈します」
まず、一杯のコーヒーを淹れるのに必要な豆の量は10〜12gとのこと。2杯目は8g〜10gと少しずつ減らして加えていきます。今回は2杯分を淹れるので20gの豆を、キッチンスケールを使って正確に計ります。次に、その豆をコーヒーミルに入れて、ハンドルを回して豆を挽いていきます。ゴリゴリとした音が変わり、ハンドルが軽くなるところまで挽いたら終了です。


次にコーヒーを淹れる前に、サーバーとコーヒカップを温めておきます。これもおいしいコーヒーを淹れるために必要なちょっとしたコツです。やかんのお湯をサーバーに注ぎ、コーヒーカップには1/3程度のお湯を淹れて温めます。コーヒーカップ全部にお湯を淹れてしまうと熱すぎてしまうので1/3程度で十分とのこと。
次に、今回の大きなポイントでもある“魔法のお湯”についてレクチャー。これはコーヒーを淹れる前のサーバーに事前に、入れるコーヒーの30%程度のお湯をいれておくこと。コーヒーの抽出後半にはどうしても抽出濃度が下がって薄くなり、さらに雑味や苦味も出てきてしまうため、事前に30%のお湯をいれておくことで、抽出前半~中盤のおいしい部分だけを使うためのテクニック!これが〈Kieido〉のやさしくまろやかで透明感のあるコーヒーの秘密だったんですね。
そして、キッチン温度計がない方でも抽出に必要な「85度」のお湯を作る方法も教えてくれました。お湯を沸かしたやかんとは別にポット(お鍋でもOK )を準備します。ポットに少しだけお湯を入れて温め、そのお湯を捨てます。そのあと、やかんのお湯をポットに全量(ポットに入るだけ全部)注ぎます。そうすると、およそ92度くらいのお湯になり、それをもう一度、やかんに戻します。そうすると、さらに温度が下がります。そしてもう一度繰り返すと88度前後に、3回目にポットに注ぐとおおよそ85度になるんだそうです。85度のお湯をつくったら必ずポットの蓋をすること。温度を下げないためにふたを必ずするようにしましょう。


次に、ペーパーフィルターをドリッパーにセットします。端の部分を折って開き、円錐形にしてドリッパーにセットします。寺内さんによれば、茶色い無漂白のペーパーではなく「白いペーパーを使ってほしい」とのこと。漂白されていないものは紙の匂いが残っており、コーヒーの味に影響するのだとか。漂白された白いフィルターのほうが紙の匂いが移らずにおいしいコーヒーを淹れることができるんだそうです。

挽いた粉をフィルターにすべて入れ、軽く振って粉の面を水平にします。中央部分に人差し指分の穴を開けます。その小さなくぼみがあることで、お湯を注ぐ時にお湯がすべって流れていかないようにすることができるんだそうです。
そして、いよいよ、ここから本番! お湯を注ぎ、コーヒーを抽出していきます。まず、小さなくぼみめがけて少しずつお湯を注ぎます。軽く「の」の字を書くように少しずつお湯を注いでいきます。ここでのポイントは、ペーパーにお湯がつかない程度の量でゆっくりと注ぐこと! ポタポタとドリッパーからコーヒーが抽出されていくくらいが適量です。一度注ぐのを止めて、30秒蒸らしたら、一気にお湯を注ぎます。

円を描くようにお湯を注いでいくのですが、お湯の水位を変えず、ずっと注ぎ続けるのがポイントです。その時、細かい泡が立ってきたらおいしいコーヒーを淹れられた証拠です。3回ほど円を描いてお湯を注いだら、まだドリッパーにお湯が残っているうちに、サーバーから外します。泡=アクなので、ドリッパーのお湯が最後まで落ち切ってしまうと雑味が入るリスクがあるので入れないほうがいいと寺内さん。


そして何よりも、お湯を注ぐスピードも重要ですが「やさしく淹れることが大事!」と寺内さん。ドリッパーとポットの距離を近づけ優しく淹れましょう。最後に、サーバーの中のコーヒーをくるりと回して撹拌し、温めておいたコーヒーカップに注いだら完成! できたてのコーヒーを温かいうちに飲みましょう!普段飲むコーヒーより優しくまろやかな味わいになり、参加者も驚いていた様子でした。
「おいしかったです。いつも飲むコーヒーより柔らかくスッキリしているように感じました」というコメントや、「今までに飲んだことのない味でした!」という参加者のコメントも聞かれました。
アイスコーヒーも同じ手順で淹れていきます。豆の量を増やし、氷の量などを調整して淹れていきます。さきほどホットコーヒーで使っていたサーバーが温まっているので、一度水で洗い熱を取ります。次にアイスコーヒーの豆を計ります。今回は2人分400ccのアイスコーヒーを作るので、さきほどのホットよりも多めの30gの豆を用意します。

今回は、400ccの4割の氷、つまり160gの氷をサーバーに入れ、そこにコーヒーを抽出していきます。400ml の目盛りまで抽出して氷がきれいに溶け切ったらアイスコーヒーが完成!グラスに入れる氷は適量で、そのあとコーヒーを注ぎ、できたてをすぐにいただきます。「苦くもなく、酸っぱくもなく、アイスコーヒーの香ばしさがある」コーヒーができあがりました。

「おいしい!」という参加者の反応が画面からも伝わってきました。「苦味がでないのが特徴の豆」ですと寺内さん。こうしてていねいに温度や分量を正確に計ることで、自宅でも〈Kieido〉さんのコーヒーが楽しめるのです!

20 年以上暮らしているという所沢の魅力を教えてもらいました!

20年以上、所沢に住んでいるという寺内さん。都内で働いていた時から所沢にお住まいでしたが、2線が使える利便性に惹かれから離れられなくなったといいます。「もう20年以上、所沢に暮らしていますが本当に便利。都内で働くことをきっかけに所沢に住み始めました。新宿線、池袋線2線があるのが利便性が高いんです」
2016年、お店を出したタイミングではまだ人通りの少なかったプロぺ通りから脇道に入った路地裏も、今ではピッツェリアやカフェなど新しいお店もできて雰囲気のいいエリアに変化。「駅前にはスーパーや駅ビルなどが多く立ち並び、住むのにとても便利な街です」と寺内さん。
また、寺内さんのコーヒー話は止まらず、参加者からの質問も飛び交いました。ミルのメンテナンスの仕方や、ドリッパーのかたちの豆知識など聞きたいことがたくさんある様子。ほかにはないやさしくまろやかなコーヒーを自宅で簡単に淹れられる〈Kieido〉さんのテクニックが満載のユニークかつ実践的なオンラインワークショップとなりました!参加していただいたみなさん、どうもありがとうございました!
★当日の様子はHanako公式インスタグラムのIGTVで動画公開中!
IGTV動画こちらをチェック!